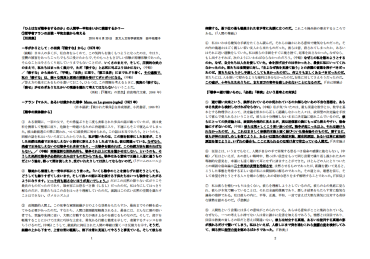本日は、二人の人物を紹介したいと思います。それが画面に映っている、フランス人で哲学者のアランと、オーストリアで活躍したユダヤ人で、精神分析学の創始者であるフロイトです。
今日のタイトルの「ひとはなぜ戦争をするのか」は、このフロイトが、1932年に国際連盟の企画でアインシュタインと交わした書簡をまとめた小さな本がありまして、その題名です。ドイツ語のタイトルを直訳すると「なぜ戦争か」といった感じになりますが、これにはいくつかの日本語訳がありまして、つい最近も新しく文庫になったものがありますので、目にされた方もおられると思います。今日はこのあとで、立木さんに、このときフロイトが何を論じたのかをお話いただけます。そしてその前段として、私はフロイトの同時代人であったアランについて、まず少しお話いたします。アランと言えば、最近彼の『幸福論』が少し注目されていますし、フランス哲学や文学に関心のある方なら、恐らくご存じの名前でしょう。ただ、必ずしも、その作品の全体が熱心に読まれているとも言い難いというか、特に哲学研究の専門的には、最近は「はやりでない」ような存在でもある人でして、今日の機会に、ぜひご紹介してみたいと思います。
ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)
アルバート アインシュタイン、ジグムント フロイト
人はなぜ戦争をするのか エロスとタナトス (光文社古典新訳文庫)
フロイト 中山 元 
Zeitgemaesses ueber Krieg und Tod. Warum Krieg? Der Briefwechsel mit Albert Einstein
Sigmund Freud Hans-Martin Lohmann 
幸福論 (岩波文庫)
アラン Alain 
ご覧の通り、この二人は19世紀の半ばから後半、日本にとっては明治維新にさしかかるころという感じですが、そのようなころに生まれ、第二次大戦に前後して亡くなっています。では今日は昔の人の話か、しかも哲学や精神分析ということであれば、いまの自分とは遠い話だ、そんな風に思われるかもしれません。ですが、もちろんそうではない。そのことをまず申しあげたいと思います。そのために、私はこれから三つのことを確認します。
第一の点は、彼らが、揃って、第一次世界大戦を経験し、それによって大きな衝撃を受けた、ということに関わります。アランは大戦が始まった時は46才で、兵役の対象ではなかったのですが、フランス軍の志願兵として前線に行っています。一方のフロイトは、ドイツとともに敗戦国となったオーストリアのウィーンで、戦後、戦争の後遺症に深刻に悩まされる多くの元兵士たちを診察することになりました。彼らはそうやって、それぞれの立場から戦争をつぶさに分析して、「人間はなぜ戦争をするのか」という問題、そして、戦争をなくすことはできるのか、そのためにはどうしたらよいのか、という問題に取り組みました。
ところで、第一次世界大戦とは、現代的な戦争の最初の事例です。そこに関わっている国家間の関係性が非常に複雑化しているということ、あるいは、国家的な工業化支援が軍事に向けられたときに、いったい何が起こるのかといった点で、アランにとってもフロイトにとっても、それは似たような事例を歴史のなかに探すことのできない、人間の歴史のなかで初めて起きてしまった異様な出来事でした。
ただ、これを逆にして考えれば、私たちにとっては、そこで彼らが体験した戦争こそが、まさしく戦争というものではないでしょうか。第一次大戦はちょうど百年前、1914年から1918年まで続いたものですが、このとき、戦争というもののありようは劇的に変わりました。戦争は単純な二国間対立の姿をとることは少なく、そのため各陣営がどれだけ疲弊しても、簡単には終わらせられない。そして戦争がずるずると長引くその間に、各国は互いに大変な技術的工夫・革新を重ねて、その「成果」によって大量に人間を殺し合い続ける。これこそは、私たちにとっての戦争の姿です。つまり、その点で言えば、私たちは人類の長い歴史の中で百年前から始まった、ある特定の時代の中を生きている。アランやフロイトといった人たちが直面した状況は、私たちが生きている時代の出発点です。
さらに、第二の点として、彼らはそのようにして大きな世界戦争が実際に一度起こってしまったことをよく知っている上で、なおかつ、次に来るかもしれない戦争のことを考えながら、「戦争をなくす」というテーマについて論じています。これは、いま、ここにいる私たちと共通の状況だと思います。つまり、私たちは、次に日本が関わるような戦争が起こるとしたら、それは世界的な戦争につながる可能性が高いことを想定しないわけにはいきません。そのときには何が起こるか。そういう予測に基づいて議論をしているという点でも、私たちは彼らと状況を共有しているのです。
ここは強調しておきたいのですが、19世紀だ、ヨーロッパだ、あるいは西洋的、西洋近代的な考えだ、だからそれは日本の私たちのものではない、そのような距離のとりかたは、歴史を学べば一目瞭然のこととして、今日、全く意味を持ちません。およそ百年前から、確かに、この地球上のどこにも逃げ場がないような「新しい時代」が始まっていて、いまもそれが展開し続けている。そう考えるべきだと私は思います。彼らの世界は、そのまま私たちが生きている世界とつながっています。それはつまり、彼らが恐れたことは、いまも私たちが恐れるべきことである。そのように言いたいと思います。
そして、ここに関わることとして、第三の点があります。これから私はアランの反戦主義の哲学をご紹介し、それから立木さんが、フロイトが戦争という問題をどれだけ深く考えたかを論じてくださいます。
ところが、です。彼らがそれだけ知力を注いで分析したにも関わらず、彼らが経験したことは新しい歴史の第一歩でしかなかった。彼らの目の前で始まった歴史は、終わることができなかったのです。これが第三の点です。これが第三の点であって、そして、今日の出発点としたいと私が考えていることです。どういうことかというと、先ほど、彼らが恐れたことは、私たちが恐れるべきことにほかならない、と言いました。つまり、課題はまだ同じまま、残り続けている。ならば、彼らの取り組んだプロジェクトは完成しないまま、私たちに残されているのではないか。そのことを申しあげてみたいと思うのです。
ここで、アランとフロイトが戦争について論じた時期というのを、ざっと見ておきます。彼らは、主に1920年代から1930年代にかけて、「戦争とはなにか」「戦争をなくす」という問題に取り組みました。
ところで、世界史をおさらいすると、1933年にはヒトラーがドイツで政権をとって、そこからの数か月で全権委任法を成立させてしまう。つまりドイツにおいて、いわゆる緊急事態法によって、ワイマール憲法が実質的に停止されるということが起こるわけですから、特に30年代に入ってからは、彼らを取り巻く事態はかなり切迫しています。
その結果として、アランの国であるフランスでは、いわゆる隣国の脅威論が高まって、戦争を準備すべきか否かの大議論になっています。一方でフロイトは、オーストリアに住むユダヤ人でしたから、ドイツを筆頭とするファシズムの高まりの中で、あらゆる国でこのままナショナリズムが強まれば、ヨーロッパ中に散らばっていたユダヤ人が危機にさらされることを予感していたはずです。
そして、そのような状況だからこそ、もちろん彼らだけではなく、多くの人間、政治家も科学者も芸術家も、様々な形で連携して、「戦争の危機」に抵抗しようとしていた動きが、この時期にはいくらでも見つけることができるのです。彼らの議論は、その大きな流れのなかに属するものです。
ところが、皆さんもご存じのように、一次大戦の「次」の戦争、つまり「第二次世界大戦」は起きてしまいました。フロイトがアインシュタインと手紙をやりとりしたのは1932年ですが、ドイツに暮らしていたユダヤ人であるアインシュタインは、ナチスが政権をとった33年以降は難民になりまして、最終的にアメリカへ移住します。フロイトも、38年にウィーンからロンドンへぎりぎりの状態で逃げ出すという事態になって、そのまま翌年ロンドンで亡くなっています。
そしてアランの方はといえば、彼はヨーロッパ全体にわたる大きな反戦・平和主義運動のリーダーとなって、30年代を通じてずっと精力的に論陣を張り続けたのですが、1940年になりますとフランスもドイツに占領され、やがてナチス・ドイツと協調関係を結んだ当時のフランス政府は、ナチスの政策をそのままフランスでも実践します。そして、それに反対する抵抗派の地下組織と政府との間で、国内は無残な内戦状態になってしまいました。そうして、戦前、最後までドイツと軍事的に対決することに反対し続けていたアランは、戦後厳しい非難にさらされることになります。
さて、ここからはアランの反戦・平和主義について、話を絞って考えてみたいと思います。そして、私は哲学の研究者ですので、その立場から、つまり、かなりアランに共感する立場から考えたい。そのときに、少し飛躍するのですが、まずは私にとって大きな手がかりとなった、全く別の人物の遺した言葉を入り口にして、お話をさせていただきたいと思います。それが、お手元の「引用集」というプリントの冒頭、小田実さんの「「殺すな」から」という文章です。
「殺すな」から (1976年)
小田 実 
「殺すな」から:「難死」の思想 (岩波現代文庫)
小田 実 
小田実さんは皆さんご存知の通り、1965年に「べ平連」を作って、ベトナム戦争への反戦運動を皮切りに様々な独自の市民運動を展開した作家です。1932年生まれで、2007年に亡くなっています。彼は、自分のベトナム戦争に対する反対運動は、子どもだった彼が第二次世界大戦のときに見た、空襲でなすすべもなく逃げ回って、翌日には道端にたくさんころがっていた、市井の人々の黒焦げの死体から始まったものだと述べています。たとえば、こんな言い方をしています。「いくさのまえで、そして、圧倒的な武力のまえで、私たちはまったく無力で、ただ「殺すな」と必死に叫ぶよりほかない」。そのような、実際には何の意味も持たない空襲で死んだ人たちについての「殺すな」が、60年代に入って、テレビに映る、同じように逃げ惑うベトナム人について、それに向けられた銃に対して、「殺すな」と主張することにそのままつながったのだ。そんなふうに説明しています。
その小田実さんが、やがて70年代に入って、何を感じたか。それを書いたのが、お手元のプリントの、下線を引いた部分です。読んでみます。「「殺すな」から始めて、「平等」「自決」に至り、「第三世界」にまでたどり着く」。
(前略)日本人の多くが、私自身をふくめて、この気持ちを強くもつようになったのは、やはり、空襲の被害をあっちこっちでもろに受けたからで、そのもっともきびしい体験が原爆体験であった。そんなことは今さらくり返していうまでもないことだが、いくさのまえで、そして、圧倒的な武力のまえで、私たちはまったく無力で、ただ「殺すな」と必死に叫ぶよりほかにない。(中略)
/「殺すな」から始めて、「平等」、「自決」に至り、「第三世界」にまでたどり着く。その過程で、私の「殺すな」は、様々な現実と原理の挑戦を受けてボロボロになる。(中略)
/答え方の基本にあるものを書いておこう。ひとつは、この問題を考えるときに、現実の「殺すな」、「殺せ」がせめぎあうたたかいの現場を離れて考えてはならないということだ。
ここには60年代から70年代にかけての、いわゆる冷戦期の世界史を背景にしていて、多くの苦い経験が含まれているわけですが、次の一文を見ていただきたいと思います。小田実さんはこう言います。その過程で、私の「殺すな」は、様々な現実と原理の挑戦を受けてボロボロになる」。
第二次世界大戦の体験から20年、そしてベトナム戦争反対に立ち上がってから10年、その時間で、「殺すな」という叫びが「現実と原理の挑戦を受けてボロボロにな」ったのだと小田実さんは書いています。この実感を、私は非常に大切なものではないかと思います。「殺すな」という実感と同じくらい、この「ボロボロになる」という実感は、多くを教えるものだと思うのです。
それというのは、この2つの実感が、「平和主義」の主張が前提とするべき、引き受けるべき条件を教えているからです。まず、「殺すな」に挑戦する「現実と原理」とはなんでしょうか。それは、「人間の現実と原理」です。だとすれば、「殺すな」という実感もまた、「人間の現実」が生み出した、そこから得られた大きな一つの「原理」に、もともと間違いありません。ですが、それは日々重なる新たな出来事の中で、つまり積み重なるいくつもの新たな「人間の現実」の前で「ボロボロ」になるものでもあって、そしてさらに他の様々な「原理」の前で、「殺すな」と心から思った瞬間が持っていた確かさを、失ってしまうことが大いにありえる。そういった性質のものだ、ということです。これを出発点として、今日は考えてみたいと思います。
さてここからは、お手元の引用プリントの、アランの部分に目を移していただきたいと思います。アランには、第一次世界大戦の従軍経験に基づいて書かれた『マルス、裁かれた戦争』という著作があります。ご覧の通り、様々なタイトルの下で、短い断章形式で書かれていまして、この断章がアランのプロポという独特のスタイルなのですが、全部で93の断章で一冊の本になっています。この本はフランスでは1921年に出版されて、51年と86年には、日本語にも訳されています。ですが、残念ながら現在ではこの日本語訳のどちらも絶版で、古本でないと読むことができません。ですので、今日は紙いっぱいにできるだけ引用をしてきました。お時間のある時、ぜひ読んでみていただきたいと思います。今日この場では、このごく一部にしか、触れることはできません。急ぎ足ですが、ここまでお話してきたことを前提にしながら、私の思う要点を、ここからざっと強調してみたいと思います。
マルス―裁かれた戦争
アラン 白井 成雄
Mars ou la guerre jugée
Alain 
まずは【戦争の実体験から】というところをご覧いただきたいのですが、先ほど申した通り、アランは一次大戦中に志願して、厳しい前線まで行っています。これは、なんでそんなことをしたかというと、彼はパリの有名な高校の教師でして、ようするに兵役に召集される年齢の若者たちというのは、彼の教え子にあたる青年たちだったわけです。彼らだけを戦争に行かせることはしないという怒りにかられて、自分は思わず戦場に行ってしまったと、反省もこめて、彼は戦後になって書いています。ですが、彼は年長者ですし、決して頑丈な体の持主でもなく、また戦闘中に大きな怪我をしたこともあって、結果として突撃隊のような役割からは外されて、なんとか生きたまま兵役を終えて除隊になります。ですが彼の教え子たち、あるいは戦場で出会った年若い同僚たちの方は、同じ戦場で次々に死んでしまうという体験をしました。
この体験を背負って日常生活に戻ったとき、彼が実感したことを示す一節があります。②という引用を見てください。そこには「いっそ何も話さないほうがよいでしょう」という台詞があります。彼はそれを、戦場から生きて戻れた青年が感じる、大きな違和感として書いています。彼らの体験と、銃後にいた人々の理解との間に、大きなずれがあるというのです。しかも、自分の話を聴いた子どもたちは戦争をやってみたいと言う。ここで続けて、④の引用を見てください。そこでは、アランは死んだ教え子たちの手紙をすぐ焼いてしまった、返事を書いてやらなかったと書いています。そして彼らの書いた「けなげな手紙」をなじっています。「この嘘が、十年もたたぬうちに、また百万の青年を殺しかねないことになるのだ」と書いています。
② 戦地から帰還した一青年が私にこう言った。「いくら戦争のことを飾らずに話そうとしても、どうしても飾りすぎてしまいます。そして我々の話に耳を傾ける子供たちはいつも戦争をしたがるようになります。いっそ何も話さないほうが良いでしょう。」だがこの沈黙の限りない広がりこそ最良のものだったのであり、雄弁家には恐るべき徴(しるし)だったのだ。私は今にしてはっきり解るのだが、若者たちはこの点をはっきり理解していたのだ。演説はこの広い沈黙の空間を満たすことはできない。(「メカニズム」)
④ 私はいわゆる健気な手紙をたくさん読んだ。それらは確かにある意味で健気なものだった。その内の幾通かはごく親しい若い友人から来たものだった。彼らは皆、殺されてしまったか、あるいはそれに近い経験をしていた。私は彼らの手紙をすぐに焼き捨て、返事を出さなかった。なぜなら、もし出すとすれば、次のようにいわねばならなかっただろう。(中略)なぜこの私を慰めようとするのか。なぜ、自分たちは人生を愛していた。命を投げ出すのは辛かったと、最後に私にいってくれなかったのか。君たちは世間皆に対し、「主よなぜ我を見捨て給う」との非難の言葉を残すべきだったのだ。君たちはもう少し手厳しくしても良かったのだし、何よりも正しくあるべきだったのだ。君たちには、人を欺いて慰めるような権利は多分なかったのだ。女性に対してさえそうだったのだ。この嘘が、十年もたたぬうちに、また百万の青年を殺しかねないことになるのだ。(「自己欺瞞」)
この、自分の教え子たちが嘘をついたと非難する書き方は、もちろんレトリック、反語的な表現です。彼が本当に非難しなければならなかった相手は、もちろん若者たちではありません。ただ、死んでしまった彼ら、そして生きて帰っても語る言葉も見つけられない彼らに代わって、教師である、言葉のプロであるアランが喋るというときには、決して「嘘」はつくことはしない、と、この文章はそう宣言するものだと読むべきです。
そのため、この『裁かれた戦争』は、ほとんど露悪的とも映るくらい、文章表現としては皮肉に満ちています。たとえば戦争を支える愛国心、兵士たちの勇気や名誉といった観念が、次々とこの本では徹底的に分析されています。そしてこの分析は、最終的には、彼ら青年兵士たちは、要は「ツルハシ」のようなものでしかなかったのだ、というところまでたどり着きます。⑨の引用をご覧ください。摩滅して取替えられたツルハシ、という記述が出てきます。死んだ教え子たちの屍には、この程度の意味しかない。このように、アランの文章は非常に感情を抑えた、ほとんど冷たい書き方をしています。それはなぜかというと、彼がこの本で、向き合わなければならなかった敵というものがあるからです。
⑨ ここにツルハシのように手段、道具とみなされる一個の人間が存在する。なるほど仕事の際、故意にツルハシを破損はしないであろう。しかし摩滅するのは仕方がない。一週間に幾本となく、冷然とツルハシは取替えられる。この人間は他の者によってツルハシと見なされたのだ。人的資源という思想自体犯罪的である/こうした指摘を耳にした気前の良いブルジョアが、「人殺しは戦争の大原則だ」と答えた。私はこの答えを再度引用してもよい。ここで私は苛立つつもりはない。苛立てばこれまた戦争である。彼の考えも一つの意見であり、普通には当然とされる意見である。ただし、そうした意見を口にする人間が、せめて自分自身でその意見を考え出し、心に抱き、他人のせいにしないことだけは願いたい。私はといえば、いつも眼に浮かぶあの屍、絶対に埋葬したくなかったあの屍を前にして、逆の意見を抱くのである。すなわち、この世のいかなる人間にとっても、他人の死を当然かつ不可避な手段とみなしうるような目的は絶対に存在しないのだ。(中略)私は自分一人で一国民全体の意見を決定するつもりはない。むしろ、今までもそうしたように、国民の意見に従うであろう。しかしまず、私は国民の意見というものが存在することを望むのである。(「屍」)
さて、ここで、結論から先に申しあげます。その敵は、私たちの現在生きている社会全体とも完全につながっているものですし、そして、この大学という場、私たち研究者にとって重要な、学問というものについても、極めて重く関わっているものです。そして残念ながら、その敵との戦いでは、アランは決して勝利をおさめたわけではなかった、そのように言わなければなりません。
ただし、それは当然です。人間の現実のせめぎあい、原理のせめぎあいが、戦争と平和の問題にほかならないのだとしたら、それはたった一人の哲学者の人生で解決されるはずがありません。第二次世界大戦が起こり、その後も戦争は起こり続けています。この問題は終わっておりません。ですから、今日はこのアランの敵を、ここできちんと確認しておきたいと思います。
⑤の引用を見てください。こう書いてあります。「彼らは荒々しくこう言い放つのだ。戦争が起こった以上、それは避けられなかったのだ、と。これはまさしく宗教的本能と固く結びついた宿命論そのものだ」。「宿命」や「宗教的本能」、あるいはその下に「狂信」といった言葉が並びますから、ではアランの敵は何か極端な存在、狂信的な、妄信的な存在なのか、と読めてしまいそうです。
⑤ 避け難い未来という、崇拝されているのか呪われているのか解らないあの不吉な思想を、あらゆる角度から検討しなければならない。(中略)私が気づいたのは、最も深遠な数学とか、数学を基本とする物理学によって、決定論を根本から正しく認識しなかった人々は、紋切型の決定論を手放しで喜んで受入れるということだ。彼らは十分理解しないままに決定論に惚れこんでいるのだ。彼らにとっての決定論とは、表面的合理的に見えるが、実は迷信家の胸にもっぱら訴えやすい、宿命論にすぎないのだ。(中略)彼らは荒々しくこう言い放つのだ。戦争が起こった以上、それは避けられなかったのだ、と。これはまさしく宗教的本能と固く結びついた宿命論そのものだ。要するに、彼らが神のおぼしめしを信じようと、あるいは国民の集団本能、歴史的原因、あるいは単に政治的原因を信じようと、いずれの場合も、ここに見られるのは受け身で苛立っている人間だ。(「決定論」)
ですが、先ほど申し上げた通り、この本でのアランの文章はもっと反語的に読むべきだと私は解釈しています。すると、ヒントはすぐ見つかります。いまの⑤の引用を続けて読むと、こうあります。「彼らが神のおぼしめしを信じようと、あるいは国民の集団的本能、歴史的原因、あるいは単に政治的原因を信じようと、いずれの場合も、ここに見られるのは受け身で苛立っている人間だ」。
「神のおぼしめし」とともに、そのまま一列に並ぶものとして、「国民の集団的本能」、「歴史的原因」、「政治的原因」が論じられていることに注目する必要があります。つまり、ここでアランが問題にしているのは、「戦争についての説明」です。「原因」と、それによって避けられない結果とされる「戦争」というもの、その因果関係であって、また、その因果関係によってもはや戦争は事実として「説明された」ものなのだと、そう信じ込み、安心して理解している人々のありかた。これこそが、ここでは非難されているのです。
しかも、そのように説明する人々は、アランにとって極めて身近にいる人々だということがわかります。⑥の引用には、「二十年来の友情」という表現があります。または、先ほどの⑨の引用を見てください。ツルハシ、つまり道具にされた若者の死を「戦争の大原則」という言葉で説明した人は「ブルジョア」、つまりまさにアランもそうであった、社会的に言えば中の上くらいのクラスの、いわゆる普通の、そして恵まれた一般市民なのです。
⑥ 狂信とは、いうまでもなく、人間が自分の手で実現する恐るべき宿命の感情に他ならない。(中略)/私はといえば、あの悲しい戦時中、熱っぽい信念をもって同じ言葉で繰り返し説かれたあの専制的な意見を、幸運にも遠く離れて耳にせずに済ますことができた。ほとんどの人にとりついたこの頑固な宿命論は二十年来の友情を冷却させ、沈黙させるものであったが、距離を置いて見ると、こうした事態を考察する正しい道が私には間接的に解るのであった。その道とは、最悪を信じ、そして希望を持とうとする人々を頭から憎む、あの奇妙な怒りをまず解明することであった。(「狂信」)
さらに、⑩を見てください。アランの言葉を、「事実を確認せよ」と言ってさえぎるのは「賢者」、つまり「学者」です。続けて、「確かにそうだ、賢者よ。君は人類が科学に酔い痴れたここ二、三世紀の申し子なのだ」とあるので、「学者」と言っても「科学者」のことか、「理系」か、と思いたくなりますが、そうではありません。「人文科学」も、「社会科学」も、学問の歴史から考えれば、すべてここに含まれます。つまり、今日の大学にいて、このアランの批判から逃れられる者はいないと理解するべきです。
⑩ 賢者が私をさえぎり、こう言う。「事実を否認することは正しい精神のすべきことではない。そうではなく、事実を確認し、それに順応することだ。戦争は一つの事実である。それが善か悪かと問うても無駄である。」/確かにそうだ、賢者よ。君は人類が科学に酔い痴れたここ二、三世紀の申し子なのだ。(中略)政治は群衆の迷蒙でしかなく、個人は奴隷にすぎないのか。そうでないとすれば、世論の形成にあたって、個人が自分一人で、自分の力量で判断を下すべき瞬間があるはずだ。それも、皆と同じ考えしかもてない狂信家連の方法に依ってではなく、孤独と自由を意志的に守る人間の存在を前提とする、あの真に科学的な方法に依ってである。要するに、世論が戦争を可とするか否かを知る前に、自分が戦争を可とするか否かを知らねばならない。その際、私自身の思想と感情以外に、私を左右する人為的事象は存在しない。私は主権者なのだ。私が将来について何を予想するかではなく、何を望むかが問題なのだ。純粋に倫理的な問題なのである。(「主権者」)
そうだとすれば、アランは続けてこうも書いています。「私が将来について何を予想するかではなく、何を望むかが問題なのだ」。「知識に基づいた客観的予測」が問題なのではない、つまり⑬の引用のように、「選択を不要にするような決定的証拠を期待するな」と言われたとき、私たち現代の研究者は何ができるか?あるいは、何かできるのか?そのことを考えなければいけません。少なくとも、哲学研究者として、私はそのようにアランの言葉を読みたいと思います。
⑬ 最近、不滅の《パイドン》を読み返しながら、私は、選択を不要にするような決定的証拠の出現をいつまでも待ち受けている臆病な思想家のことを考えるのであった。もし我々が考える機械にすぎず、また、正義と平和が、他の純粋無垢な理念同様、疑惑に打ち勝ち、精神を支配する力強さをそれ自体で備えているとするなら、話はうますぎるというものだ。だがソクラテスは決して奴隷根性を望まなかったし、また誰一人、「正義は最強なり、真理は最強なり」と述べるような嘆かわしい思想家を望まないだろう。(中略)だが、我々は判断を下す勇気を欠いているのだろうか。確かに口先だけでは十分ではない。/だが問題を熟視しよう。悪を是認せず、崇めないこと。悪を精神的に受入れないこと。未だ存在していないものの実現に向けて断固意志することが大切なのだ。長年の間我々の眼を事実に向けさせるために払ってきた、あのひ弱な精神の並々ならぬ努力に我々は気づくようになるだろうか。あらゆる面で貪欲、尊大、矮小なこの実験器具的精神が我々を戦争に導いたことを、我々は自覚できるだろうか。あの戦争は彼らにとって自分たちの正しさの証明に他ならなかったし、我々にとっては処罰だったのだ。君たちにはあの意地悪な微笑の意味が捕えられるだろうか。さあ、わが友よ、意志せずに考えたりすることはもうやめるがよい。そしてまず大きな誓いをたてよ。なぜなら君が傍観し、待っているだけなら、それは賛成することだ。もし戦争に否と言うなら、それは断固として否なのだ。(「意志すること」)
そしてそのように読みますと、アランの提言は、はっきりと読み取ることができます。最後に、⑪の引用を見てください。このように書かれています。「現実ではなく、理想が問題となる時は、このように振る舞わねばならない。精神的譲歩は一歩たりともせず、固く戦争を否定せよ」。この文章はそのまま、次のように言い替えられると思います。「戦争に対しながら、平和を構想するときは、このように振る舞わねばならない。精神的譲歩は一歩たりともせず、固く平和を肯定せよ」。
⑪ 戦争が人為的な、純粋に人為的な事象であり、その一切の原因が人々の意見にあることをしっかり自覚しよう。そしてこの際、最も危険な意見とは、戦争は切迫しており、不可避だと、皆に信じこませる意見であることに注目しよう。(中略)ここに有害な一つの意見があるとする。この意見は場合によっては真実なものとなるかもしれないが、それは大多数がその意見を心に抱いた場合に限られる。以上を言いかえるなら、種々の意見がからみあって作られている人間界の事象の場合は、真実は確認されるものでなく、作りあげられるものだということである。だから認識するだけでは十分でない。判断という美しい言葉のもつ最上の意味で、我々は判断を下さなければならない。/この迷妄に対抗する証拠を探してはならない。自由な人間が戦争反対を表明しない限り、証拠など存在しないのだ。だがもし君が戦争反対を決意すれば、それは強力な証拠となろう。だから種々の証拠に助けを求めず、松葉づえにたよらず、一人で歩くがよい。君自身の内心の指示に従い、主権者として決定を下すがよい。現実ではなく、理想が問題となる時は、このように振舞わねばならない。精神的譲歩は一歩もたりともせず、固く戦争を否定せよ。戦前も、戦中も、戦後もそうすべきだ。なぜなら、人々の賛同こそ戦争に生命を与えるものであることを、君はよく承知しているではないか。何よりもまず戦争に養分を与えないことだ。(「判断」)
ところで、アランの文章をさらに細かく読みこんでみますと、そこにはもう一つのキーワード、「意志」、つまり「意志を持つこと」・「意志すること」という、重要なキーワードも発見することができます。この「意志すること」が、実はとても難しいことなのだというのが、アランの生きていた時代には、様々な形で、人間について強く意識され、論じられるようになっていました。ですが、それでも、そこに懸けなくてはならない。これが、彼の生きた時代に対して、アランの出した結論だったのだと理解することができます。
さて、このように確認して、私の話はここでいったん止めたいと思います。そしてここからは、人間が意志すること、その難しさにこそ、まさしく根本から取り組んだ人物として、フロイトの議論を聴きたいと思います。